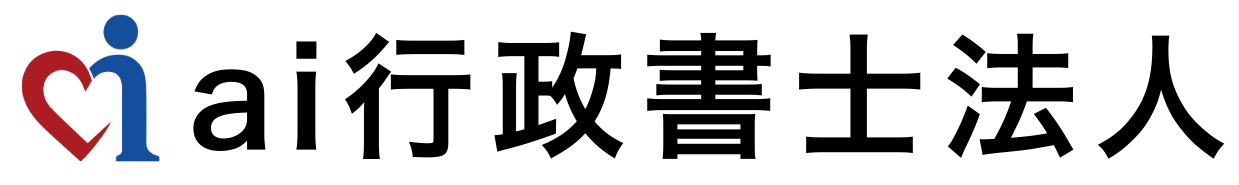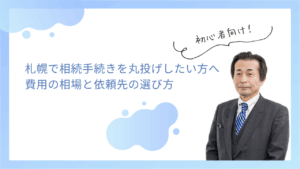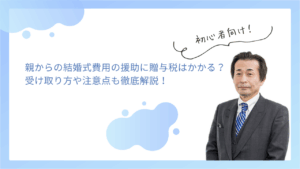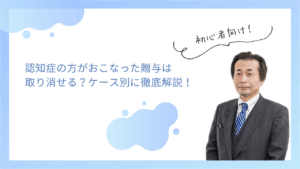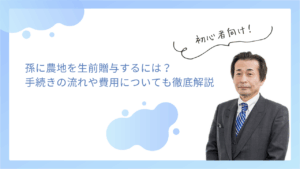孫への生前贈与は7年の持ち戻しの対象外になる?事例別に徹底解説!

「孫への生前贈与も7年以内の贈与は相続税に戻されるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
実はこの7年ルールは、全ての贈与に適用されるわけではなく、孫への贈与は原則として対象外で扱われます。ただし、孫の立場や相続の形によっては例外も存在します。
本記事では、7年ルールの基本から、対象になるケース・ならないケース、具体的な事例や節税のポイントまでを、わかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
【結論】孫への生前贈与は基本的に7年の持ち戻しの対象外になる
結論からいうと、孫への生前贈与は原則として相続税の「7年以内持ち戻し」の対象外です。
持ち戻しの対象となるのは、相続人(配偶者・子など)への贈与が基本であり、相続人ではない孫への贈与は、たとえ被相続人の死亡前7年以内であっても相続財産に加算されません。
そのため、孫への生前贈与は相続税対策として有効な手段と言えます。ただし、孫が遺言で財産を受けとる「受遺者」や、生命保険金の受取人になる場合は例外的に扱いが変わる点には注意が必要です。

そもそも生前贈与の持ち戻しルールとは?
生前贈与の持ち戻しルールとは、被相続人が亡くなる前一定期間内に行った贈与を、相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
これは、相続直前の駆け込み贈与による節税を防ぐ目的で設けられています。
対象となるのは、被相続人から相続人に対して行われた贈与で、基礎控除(年間110万円)以内の贈与であっても加算対象となってしまいます。
なお、持ち戻された財産自体が再度課税されるわけではなく、相続税の計算上、相続財産に合算されるしくみです。
令和6年に3年→7年に改正
令和6年(2024年)以降の贈与から、生前贈与の持ち戻し期間は従来の3年から7年へと段階的に延長されました。
この改正により、相続開始前7年以内に相続人へ贈与した財産は、相続税の課税対象となってしまいます。ただし、いきなり7年分全てが対象になるのではなく、延長された4年分については総額100万円まで控除される経過措置があります。
この改正は、相続税と贈与税を一体的に捉えた課税強化が目的であり、相続人への節税目的の生前贈与は、以前より効果が限定的になっています。
相続税との関係は?
生前贈与は、相続税対策として活用されることが多いものの、誰に贈与するかで相続税への影響は大きく異なります。
相続人への贈与は7年以内であれば相続税に加算されますが、相続人でない孫への贈与は原則として加算されません。
そのため、孫への生前贈与は相続財産そのものを減らす効果があります。ただし、孫が相続や遺贈により財産を取得すると「相続税額の2割加算」が適用される点には注意が必要です。
贈与と相続をセットで考えた計画が重要です。
孫への生前贈与が7年の持ち戻しの対象となる場合は?
孫への贈与は原則として7年ルールの対象外ですが、全てのケースで必ず対象外になるわけではありません。
孫が相続人として扱われる立場になった場合や、相続と同様の財産取得をする場合には、例外的に持ち戻しの対象となることがあります。
ここでは、どのような場合に孫への贈与が7年ルールに該当してしまうのか、代表的なケースごとに解説します。
孫が「代襲相続人」として相続人になる場合
代襲相続とは、本来相続人となるはずの子が被相続人より先に死亡している場合などに、その子の直系卑属である孫が相続人になる制度です。
この場合、孫は法律上の相続人となるため、被相続人から孫への生前贈与は、相続開始前7年以内であれば持ち戻しの対象です。
たとえ贈与当時は相続人でなかったとしても、結果的に代襲相続人として相続すれば、相続税の計算では相続人への贈与と同様に扱われます。相続発生の可能性を見越した贈与には注意が必要です。

孫が「養子」となって法定相続人になる場合
孫を養子にした場合、その孫は実子と同じ法定相続人として扱われます。
そのため、養子縁組後に行った孫への生前贈与は、被相続人の死亡前7年以内であれば持ち戻しの対象となってしまいます。
また、養子縁組前の贈与であっても、相続時点で法定相続人となっていれば加算対象とされる可能性があります。相続税対策として孫養子を検討するケースもありますが、生前贈与の持ち戻しや相続税の2割加算など、税務上の不利が生じる場合もあるため慎重な判断が必要です。
孫を遺言で相続財産の受取人として指定している場合
孫を遺言で財産の受取人に指定する場合、孫は「受遺者」として扱われます。
受遺者は相続人ではありませんが、相続税法上は相続人に準じた扱いを受けるため、被相続人の死亡前7年以内に行った生前贈与は持ち戻しの対象です。この場合、孫への贈与は相続税計算上、相続財産に加算されるため、贈与による節税効果は限定的になってしまします。
さらに、孫は相続税額の2割加算の対象にもなるため、遺言と生前贈与を併用する場合は全体の税負担を考慮する必要があります。
孫が生命保険金の受取人に指定されている場合
孫が生命保険金の受取人に指定されている場合、孫は「みなし相続財産」の取得者として扱われます。
この場合も、相続税法上は相続人に準ずる立場となるため、被相続人の死亡前7年以内に孫へ行った生前贈与は持ち戻しの対象になる可能性があります。生命保険金には非課税枠がありますが、これは法定相続人の数に応じて計算されるため、孫が法定相続人でない場合は非課税枠が使えない点にも注意が必要です。
【事例で解説】孫への贈与は7年ルールに当てはまる?当てはまらない?
孫への贈与であっても、相続人になる場合や、非課税制度を利用する場合など、状況によって扱いは大きく変わります。
ここでは、実際によくある3つのケースを取り上げ、それぞれ7年ルールに該当するのかどうかをわかりやすく整理していきます。
事例①親が先に亡くなり孫が相続人となったケース
祖父が生前に孫へ現金を贈与していたものの、そのあと、孫の親である子が祖父より先に亡くなり、孫が代襲相続人として相続人になったケースです。
この場合、孫は法律上の相続人となるため、祖父の死亡前7年以内の贈与は持ち戻しの対象となってしまいます。
贈与当時は相続人ではなかったとしても、相続開始時点の立場が重視されるため、将来的に代襲相続が発生する可能性がある場合、孫への贈与でも相続税に影響する点に注意が必要です。
事例②孫への教育資金として毎年贈与したケース
祖父母が孫の学費や習い事のため、毎年一定額を贈与していたケースです。
通常、教育費や生活費として、その都度必要な金額を直接支払っている場合は贈与税も相続税も非課税となり、7年ルールの対象にもなりません。
また、教育資金贈与の非課税特例を利用している場合も、一定条件を満たせば相続財産への持ち戻しはありません。ただし、まとめて渡して貯蓄された場合は贈与と判断される可能性があるため、支払い方法には注意が必要です。
事例③孫へ住宅購入費用の資金を渡したケース
祖父母が孫の住宅購入のためにまとまった資金を贈与したケースです。
孫が相続人でない場合、通常の生前贈与であれば7年ルールの対象外です。また、住宅取得等資金の贈与の非課税特例を利用していれば、一定額まで贈与税がかからず、相続税への持ち戻しもありません。
ただし、孫が将来、代襲相続人や受遺者となる場合は、7年以内の贈与が加算対象となる可能性があります。贈与時だけでなく将来の相続関係も踏まえた判断が重要です。
孫へ生前贈与する際の注意点
孫への生前贈与は節税効果が高い一方で、やり方を誤ると贈与が否認されたり、思わぬ課税を受けたりするリスクがあります。
特に、名義預金の問題や、贈与方法の選択ミスはトラブルになりやすいポイントです。ここでは、孫へ生前贈与をおこなう際に必ず押さえておきたい注意点を整理します。
贈与の証拠を残し、名義預金扱いされないようにする
孫への贈与でもっとも多いトラブルが、名義預金と判断されて贈与が否認されるケースです。
通帳や口座は孫名義でも、祖父母が管理し、孫が自由に使えない状態では贈与と認められません。これを防ぐためには、贈与契約書を作成し、贈与日・金額・当事者を明確にするのが重要です。
また、振込記録を残し、通帳や印鑑は原則として孫本人が管理する形にします。未成年の場合でも、使途や管理方法を明確にしておくことで、税務調査時のリスクを下げられます。
孫の年齢・目的に合わせた贈与方法を選ぶ
孫への贈与は、年齢や使い道に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
幼少期であれば、教育費や生活費を必要な都度支払う方法が非課税で安全です。進学や留学が見えている場合は、教育資金贈与の非課税特例の活用も検討できます。成人後であれば、年間110万円の基礎控除内で計画的に贈与する、住宅取得資金の特例を使うなど選択肢が広がります。
目的に合わない贈与は、課税リスクや無駄な税負担につながるため注意が必要です。
将来の相続を見据えて税理士・専門家に一度相談しておく
孫への生前贈与は、将来の相続関係によって税務上の扱いが大きく変わるため、早い段階で専門家に相談しておくことが重要です。
代襲相続や養子縁組、遺言の内容によっては、贈与が7年ルールの対象になる可能性もあります。また、贈与税と相続税のどちらが有利かは、家族構成や財産内容によって異なります。
税理士などの専門家に一度相談すれば、制度の使い分けや書類の整備方法まで含めた、無理のない贈与計画を立てることができます。
孫へ生前贈与するメリット
孫への生前贈与には、相続税対策以外にもさまざまなメリットがあります。
親世代を飛ばして資産を承継できる点や、非課税制度を活用できる点は、ほかの方法にはない大きな特徴と言えるでしょう。ここでは、孫への生前贈与で得られる主なメリットについて、具体的に解説していきます。
相続税対策として効果がある
孫への生前贈与は、相続税対策として非常に効果的です。
通常、相続人への贈与は死亡前7年以内であれば相続財産に持ち戻されますが、相続人でない孫への贈与は原則として持ち戻しの対象外です。そのため、生前に財産を孫へ移しておくことで、将来の相続財産そのものを減らすことが可能です。
また、毎年110万円以内の基礎控除を活用して計画的に贈与すれば、贈与税をかけずに資産を移転できます。早めに始めるほど節税効果は高くなると言えるでしょう。
親を経由せず、直接孫へ資産を渡せる
孫への生前贈与の大きなメリットのひとつが、親世代を経由せずに直接孫へ資産を渡せる点です。
通常の相続では、祖父母の財産はいったん子が相続し、そのあとさらに孫へ引き継がれるため、二世代分の相続税がかかる可能性があります。生前に孫へ贈与しておけば、この二重課税のリスクを抑えることができます。
また、子世代に十分な資産がある場合や、孫の教育・住宅取得など具体的な目的がある場合にも、直接贈与は柔軟な資産承継手段となるでしょう。
非課税特例を利用できる
孫への生前贈与では、複数の非課税特例を活用できる点も大きな魅力です。
代表的なものとして、教育資金贈与の非課税特例や、住宅取得等資金の贈与の非課税特例があります。これらを利用すれば、数百万円から数千万円規模の資金を非課税で贈与するのも可能です。さらに、日常的な教育費や生活費を必要な都度支払う場合も贈与税はかかりません。
制度の要件を満たすことが前提となるため、事前確認と適切な手続きが重要です。
孫への生前贈与で節税するポイント
孫への生前贈与の効果を最大限に高めるには、複数の制度を正しく組み合わせて使うことが重要です。
教育資金や住宅資金の非課税制度、暦年贈与、特例税率など、それぞれ特徴が異なります。ここでは、孫への贈与で節税するために押さえておきたい具体的なポイントを順に解説します。
「教育資金の贈与非課税制度」を賢く使う
教育資金の贈与非課税制度は、祖父母から孫へ教育目的の資金を最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。
学校の授業料や入学金だけでなく、塾代や習い事費用なども対象です。利用には金融機関で専用口座を開設し、支払いのたびに領収書を提出する必要があります。
孫が30歳になると制度は終了するため、進学予定や教育費の見通しを立てたうえで活用するのが重要です。
孫の住宅取得資金に使える非課税制度も検討する
孫が住宅を購入・新築する際には、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を活用できます。
省エネ住宅など一定の要件を満たす場合、最大1,000万円程度まで非課税となり、通常の基礎控除との併用も可能です。対象となる住宅や贈与時期、孫の所得要件など細かな条件が定められているため、事前確認が不可欠です。
将来の住居取得が見込まれる場合、大きな金額を一度に贈与できる点が大きなメリットです。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用する
結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度を使えば、孫へ最大1,000万円まで非課税で贈与できます。
結婚式費用や新生活の準備費用、妊娠・出産・育児に関する支出が対象です。教育資金と同様に専用口座を利用し、支出の証明が必要です。孫が50歳に達すると制度は終了し、未使用分は課税対象となるため、計画的な利用が重要です。
結婚や出産のタイミングに合わせた活用が効果的です。
暦年贈与の基礎控除を利用する
暦年贈与の基礎控除は、毎年110万円まで贈与税がかからない制度で、孫への贈与でも利用できます。
特別な手続きが不要で、柔軟に使える点が大きなメリットです。長期間にわたってコツコツ贈与を続けることで、相続財産を着実に減らすことができます。
ただし、毎年同額を贈与し続けると「定期贈与(あらかじめ決めた金額を決めた期間・回数にわたって継続的に贈与する契約とみなされ、毎年の基礎控除が使えず、贈与総額に対して一括で贈与税が課される可能性がある贈与)」と判断されるリスクがあるため、贈与額や時期を変えるなど工夫が必要です。
生活費・教育費の都度贈与はそもそも非課税
孫の生活費や教育費として、必要な都度、直接支払う場合は贈与税がかかりません。
学費、教材費、下宿代など、日常生活に必要な範囲であれば非課税となり、金額の上限もありません。ただし、まとめて渡して貯蓄に回した場合は贈与と判断される可能性があります。
支払い先へ直接振り込む、領収書を保管するなど、使途が明確になる形で支払うことが重要です。
18歳以上の孫への贈与は「特例税率」が適用される
18歳以上の孫に贈与をおこなう場合、贈与税の計算において「特例税率」が適用されます。特例税率は、直系尊属(祖父母・父母)から18歳以上の子・孫へ贈与するケースを想定した税率で、下記のように一般税率よりも税負担が軽くなるように設計されています。
▼贈与税の特例税率
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
▼計算方法
(贈与を受けた財産の額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
そのため、基礎控除(110万円)を超えるまとまった金額を贈与する場合でも、通常より低い税率で贈与税を計算でき、計画的な生前贈与による節税効果が高まります。
まとめ
孫への生前贈与は、原則として7年の持ち戻し対象外であり、相続税対策として非常に有効な手段です。
ただし、代襲相続や遺言、養子縁組などによって孫の立場が変わると、例外的に7年ルールが適用される場合もあります。
重要なのは、「孫だから大丈夫」と思い込まず、将来の相続関係まで見据えて贈与の設計をおこなうことです。制度を正しく理解し、必要に応じて専門家の助言を受けながら進めることで、安心かつ効果的な資産承継につながります。
孫への生前贈与や相続税対策について少しでも不安がある場合は、制度に精通した専門家への相談が大切です。具体的なケースに応じた最適な方法を知りたい方は、ぜひ当法人「ai行政書士法人」にご連絡ください。